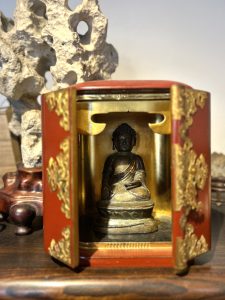松竹梅があってよかった…。(愛知県名古屋市千種区姫池通 骨董買取 古美術風光舎)
2024.12.10
先日から、飾っている松の盆栽が目を引きます。

実家の松を選定していた亡き父を思い出すのですが、興味などさらさらなかったものですが、どうやって剪定していたのか…もう少しちゃんと聞いておけばよかったな。と、今さら思ったりしておりました。
さてさて、本日のつぶやきはそんな「松」のつぶやきなのです。
先日お蕎麦屋さんで定食を注文したのですが、例の如くランク付けが「松竹梅」(しょうちくばい)でありました。先日も「松」じゃなくて「竹」を注文。これを「極端回避」(極端な選択による損失の可能性を避けようとして真ん中を選んでしまう心理)というらしいのですが、私のような人はけっこう多いらしいようです。ちなみに「竹」の定食美味しかったですよ。
こんなふうに松竹梅は飲食店のメニューなどに多く使われますが、「特上・上・並」を「松・竹・梅」とすることで、お客さんが気兼ねなく注文できるようにという意図があるようです。また、うなぎ屋で「待つ(待つ)だけ(竹)うめえ(梅)」なんて洒落ているという語たとも言えるようです。
そんな松竹梅の由来は、松は常緑樹で冬でも緑の葉を保つことから「長寿・延年」、竹は折れにくい植物で「成長・生命力」のシンボル、梅は苔が生えるくらいの樹齢になっても春になると美しい花を咲かせることから「長寿・気高さ」の象徴とされ、松も竹も梅もめでたい言葉として使われる言葉。平安時代から縁起物として用いられているようなのですが、三つの等級に分ける際に通常は「松」が最上級になったのはなぜでしょうか。
諸説あるのですが、一つは「語呂がいいから」という説。
確かに「梅竹松(ばいちくしょう)」「竹梅松(ちくばいしょう)」ではしっくりきませんが、これは慣れということもあるでしょうか。また、「松は仙人が食べるという言い伝えがあるから最高級になった」「お目出度いものとして定着した順番」など色々な説がありますが、どの説も、もともとは松竹梅に序列はなかったという点では一致しています。また、縁起物として扱われるようになった歴史の古さ順で、松が平安時代、竹が室町時代、梅が江戸時代からといわれているからなど諸説様々であります。
それにしても懐が寒くても、お寿司屋さんでは「並」とは注文しにくいし、そうした消費者の心理に配慮して松竹梅が等級に割り当てられたとも言えるのですが、いやはや「並」の代わりに使われた梅にとっては迷惑な話のような気もしますが、そんな「松竹梅」のランク付けは庶民の自分にとってはありがたい限りです。
「松竹梅」みんなめでたくてみんないい呼び名ではありますが、ほんとうは「松で!」と、大きな声で注文してみたいのは正直なところであります笑。
それではごきげんよう。(スタッフY)
I have been seeing the pines in the store since the other day.
It reminds me of my late father who selected the pine trees at my parents’ house… I had no interest in them, but I wonder how he pruned them… I sometimes wonder now if I should have listened to him more carefully. Today’s tweet is about “Matsu.
The other day, I ordered a set meal at a soba (buckwheat noodle) restaurant, and as usual, it was ranked on a scale of “pine,” “bamboo,” and “plum” (shohtakubai). The other day, I chose “bamboo” instead of “pine,” and it seems that there are many people who have such extreme aversiveness (a psychological tendency to choose the middle to avoid the possibility of loss due to extreme choices).
It is said that the “Matsu, Take, and Ume” are often used in restaurant menus and the like, with the intention of allowing customers to order without hesitation by using “Matsu, Take, and Ume” for “Tokujo, Jojo, and Nami,” and it is also said to be a pun on the long wait at an eel restaurant, “Wait (Matsu) only (Take) Ume (Ume) E”. It is also said to be a pun on the long wait at an eel restaurant.
The origin of the words “pine,” “bamboo,” and “plum” is that pine trees are evergreen and keep their green leaves even in winter, symbolizing “longevity and longevity,” bamboo is a plant that is hard to break and symbolizes “growth and vitality,” and plum trees bloom beautiful flowers in spring even when they are so old that moss is growing on them, symbolizing “longevity and nobility. Pine, bamboo, and plum are all used as words of good fortune. They have been used as good luck charms since the Heian period (794-1185), but why was “Matsu” usually given the highest rank when divided into three grades?
There are various theories, but one theory is that it is because it is a good word. Certainly, “bai chikumatsu” and “chikubai shou” do not fit well, but this may be a matter of habituation. There are also various theories, such as “pine trees are said to be eaten by hermits, so they became the highest class” or “the order of pine trees was established as something auspicious,” but all theories agree that originally there was no pecking order among pine, bamboo, and plum trees. There are also various theories about the order of the history in which they came to be treated as lucky charms, with pine trees dating from the Heian period (794-1185), bamboo from the Muromachi period (1333-1573), and plum from the Edo period (1603-1868).
It is hard to order “Nami” at sushi restaurants even if you are hungry, and it can be said that the Matsu, Take, and Ume grades were assigned in consideration of such consumers’ mentality. However, the “Matsu, Take, and Ume” ranking is a blessing for me as a commoner.
But I am grateful for the rank of “Matsu, Bamboo, and Ume” because I am a commoner. I would like to order “Matsu” in a loud voice.
Have a good day.
*******************
ご実家の整理やお片付けなどをされている方のご相談などが多くございます。
お片付けなどくれぐれもご無理のないようになさってくださいませ。
風光舎では古美術品や骨董品の他にも絵画や宝石、趣味のお品など様々なジャンルのものを買受しております。
お片付けをされていて、こういうものでもいいのかしらと迷われているものでも、どうぞお気軽にご相談下さいませ。
また風光舎は、出張買取も強化しております。ご近所はもちろん、愛知県内、岐阜県、三重県その他の県へも出張いたします。
まずは、お電話お待ちしております。
愛知県名古屋市千種区姫池通
骨董 買取【古美術 風光舎 名古屋店】
TEL052(734)8444
10:00-18:00 OPEN
#出張買取#骨董#古美術#骨董品#絵画#版画#茶道具#刀剣#彫刻