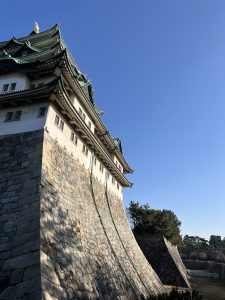ホワイトデーお返ししましたか?(愛知県名古屋市千種区姫池通 骨董買取 古美術風光舎)
2023.03.14
みなさまこんにちは、スタッフNでごさいます。
最近、運動不足で力が有り余っております。
ウィメンズマラソンの話題が出ましたが、実はNも1人でジョギングできるようになりたいとひそかに思っております。
しかし、学生時代に走り方を笑われて以来、どうも人前で走れません。
チーム風光舎としていつかマラソンに参加できたら楽しそうですね。
陸上部の知人に、教えてほしいと頼んでいるのですが、仕事も忙しいのか教えてもらえません。
仕方ないので、しばらくは自転車で爆走することにいたします。
今日はホワイトデーでございます。
知人にプレゼントしたジブリパーク、アリエッティとGODIVAコラボのチョコの画像が届きました。
購入した際には気が付かなかったのですが、2段になっていてとてもかわいいです。

ホワイトデーとは、一般的に3月14日に、バレンタインデーにチョコレートなどをもらった男性がそのお返しとしてキャンディ、マシュマロ、ホワイトチョコレートなどのプレゼントを女性へ贈る日とされております。
ホワイトデーの習慣は日本で生まれ、中華人民共和国や台湾、韓国など東アジアの一部でも見られます。
欧米やオセアニア、南アメリカやアフリカなどその他の世界各国ではこういった習慣は見られないそうです。
ただし、近年(2000年代以降)の日本では、「友チョコ」や「自分チョコ」、「義理チョコ」などバレンタインデーの習慣が多様化してきていることから、ホワイトデーにも「友チョコ」や「義理チョコ」のお返しが行われるなど多様化が見られます。
ホワイトデーの起源については諸説あり、ホワイトデーの時期になると様々な企業、各陣がそれぞれ「元祖」だと主張しております。
近年ではデパートなどで食品以外の贈り物などの販売促進も行われており、菓子業界では駅やデパートでの手焼きクッキーなどの販売も売り上げを伸ばしているとされ、現在の市場規模は約750億円に上ると言われるとか。
日本でバレンタインデーが定着するに従って、菓子業界でそれにお返しをする日を作ってはどうかという案が出されました。
これを受けた菓子業界では、昭和40年代に入って以降、個々に独自の日を定め、ビスケットやマシュマロ、キャンディ等を「お返しの贈り物」として宣伝販売するようになりました。
不二家もまた「リターン・バレンタイン」という名称でバレンタインデーのお返し用菓子類の宣伝販売を行うようになり、1973年(昭和48年)にエイワと協力して3月14日にマシュマロを販売するキャンペーンを開始いたしました。
黄身餡をくるんだ白いマシュマロ菓子の「鶴乃子」で知られる福岡市の老舗菓子屋「石村萬盛堂」の社長は、バレンタインデーのお返しにせめてマシュマロでも渡してほしい旨の文章が少女雑誌に掲載されているのを目にしました。
石村萬盛堂はこの文章に触発され、バレンタインデーの返礼としてマシュマロを渡す日を創設し、返礼用マシュマロ菓子として「君からもらったチョコレートを僕の優しさ(マシュマロ)で包んでお返しするよ」とのコンセプトで、黄身餡の代わりにチョコレートをくるんだマシュマロを売り出すこととしました。
この「マシュマロデー」は、百貨店岩田屋のアドバイスで、当時大型のイベントが無かった時期にあたる3月14日に設定され、1978年(昭和53年)3月14日からキャンペーンが開始されました。
後に、他業界にもこのキャンペーンを拡張するため、1980年代に百貨店側からの申し出により名称をホワイトデーに変更したそうです。
全国飴菓子工業協同組合(全飴協)は、1978年(昭和53年)に「キャンディを贈る日」としてホワイトデーを制定し、2年後の1980年(昭和55年)より三越・電通の協力も得てイベントやキャンペーンをスタートさせました。
ホワイトデーを3月14日に定めた理由は、269年2月14日、兵士の自由結婚禁止政策に背いて結婚しようとした男女を救うためにウァレンティヌス司祭は殉教しましたが、その1ヶ月後の3月14日、その2人が改めて永遠の愛を誓い合ったとされていることや、古事記および日本書紀で日本において初めて飴が製造されたとされる日が3月14日前後とされていることに由来しております。
ホワイトデーという名称は、英和辞典のホワイトの項に、シュガーやスイートといった解説が記載されており、若者の純愛や砂糖をイメージさせることによるものであるからだそうです。
ハンカチ類もホワイトデーの返礼品として人気がございます。
コミックシーモアが2016年2月に調べたアンケートによると、20代から30代の女性が希望するホワイトデーの返礼の金額は、最頻値は「500円未満」の27%、次いで「500円~1,000円未満」の24%でございました。
ブライダルジュエリー専門店の銀座ダイヤモンドシライシが2016年2月に調べたアンケートによると、20歳から35歳の男性が、好きな人(本命)へホワイトデーの返礼をする時の平均予算は、最頻値は「500円から1000円未満」の22.0%、次いで「1,000円~2,000円未満」の21.2%でした。
また、33.6%の男性が、「貰ったものの金額よりやや多くお返しする」と回答し、次いで28.0%が「同額程度」、次いで14.4%が「お返ししない」と回答いたしました。
阪神百貨店梅田本店が2016年1月に調べたアンケートによると、45%の女性がホワイトデーの返礼に「がっかりした」と回答しているとか。
また85%の女性が、事前に好みを調べてほしいと回答したそうです。
また、同じアンケートによると、男性が返礼するときの予算は、最頻値は「もらった額と同等」の33%、次いで「2倍」の27%、次いで「1.5倍」の25%でした。
そして、「女性の好みをリサーチする」と回答した男性は49%だったそうです。
チョコレートが大半を占めるバレンタインデーと異なり、ホワイトデーは菓子類だけでなく、近年は食品以外のプレゼントも好まれるようになっております。
JIONの2017年の調査によれば、女性側の希望では菓子類は2位で、1位はピアスやネックレスなどのアクセサリーとなっております。
Nも昔、小学生が喜びそうな小物入れをいただいて、苦笑いしたことがあります。
自分のために選んでくれたことが嬉しいので、いまだに使っておりますが、中々難しいですね。
アジアの一部の国でもホワイトデーの習慣が行われております。
中国語では「白色情人節」と表記します。
台湾での贈り物は様々で、韓国では、バスケットに菓子類を盛り合わせデコレーションしたものが返礼品の定番とされているとか。
欧米やオセアニア、南アメリカやアフリカなどその他の世界各国ではこういった習慣は見られないそうです。
世界共通ではないんですね。
少し施行を変えて、骨董品のプレゼントも面白いかもしれませんよ。
ではでは

Hello everyone, I’m Staff N.
Recently, I have a lot of strength due to lack of exercise.
The topic of the women’s marathon came up, but in fact, N is secretly hoping to be able to jog by herself.
However, since I was laughed at for the way I ran when I was a student, I can’t run in front of people.
It would be fun to participate in a marathon someday as a member of Team Fukousha.
I asked an acquaintance from the track and field club to teach me about it, but he couldn’t tell me because he was busy with work.
I can’t help it, so I’m going to blast by bicycle for a while.
Today is White Day.
I received an image of Ghibli Park, Arrietty and GODIVA collaboration chocolate that I gave to an acquaintance.
I didn’t notice it when I bought it, but it’s two-tiered and very cute.
White Day is generally celebrated on March 14th, when men who received chocolates on Valentine’s Day give presents such as candies, marshmallows, and white chocolate to women in return.
The custom of White Day originated in Japan and can be seen in parts of East Asia such as the People’s Republic of China, Taiwan, and South Korea.
It seems that this custom is not seen in other countries around the world such as Europe, America, Oceania, South America and Africa.
However, in recent years (since the 2000s) in Japan, Valentine’s Day customs have diversified, such as “tomo choco”, “jiri choco”, and “giri choco”. Diversification can be seen, such as giving back chocolate.
There are various theories about the origin of White Day, and when it comes to White Day, various companies and groups claim that it is the “originator”.
In recent years, department stores have been promoting sales of gifts other than food, and in the confectionery industry, sales of hand-baked cookies at stations and department stores are said to be increasing, and the current market size is about 75 billion. It is said that it goes up to the circle.
As Valentine’s Day became more established in Japan, it was suggested that the confectionery industry should create a day to give back to Valentine’s Day.
In the confectionery industry, in response to this, from the 1960s onwards, each individual set its own date and began to advertise and sell biscuits, marshmallows, candies, etc. as “gifts in return.”
Fujiya also began advertising and selling Valentine’s Day return sweets under the name of “Return Valentine”, and in 1973 (Showa 48), in cooperation with Eiwa, a campaign to sell marshmallows on March 14th. has started.
The president of Ishimura Manseido, a long-established confectionery shop in Fukuoka known for Tsurunoko, a white marshmallow confectionery wrapped in egg yolk, wrote in a girl’s magazine that he would like at least a marshmallow in return for Valentine’s Day. I saw it posted.
Manseido Ishimura was inspired by this sentence and established a day to give marshmallows as a return gift for Valentine’s Day, and as a return gift marshmallow confectionery, “I will return the chocolate you gave me by wrapping it in my kindness (marshmallow).” With this concept, we decided to sell marshmallows wrapped in chocolate instead of yolk bean paste.
This “Marshmallow Day” was set on March 14th, when there were no large-scale events at the time, on the advice of the department store Iwataya, and the campaign began on March 14th, 1978.
Later, in order to extend this campaign to other industries, the name was changed to White Day at the request of department stores in the 1980s.
In 1978, the National Candy Industry Cooperative Association (Zenamekyo) established White Day as a day to give candies, and two years later in 1980, Mitsukoshi and Dentsu started to cooperate. We have also started events and campaigns.
The reason why White Day was set on March 14 is that on February 14, 269, Priest Valentinus was martyred to save a man and a woman who tried to marry against the policy of prohibiting free marriage for soldiers. Later on March 14th, it is said that the two of them once again pledged their eternal love to each other, and according to the Kojiki and Nihonshoki, the day when candy was first manufactured in Japan is said to be around March 14th. It is derived from the fact that
It is said that the name White Day comes from the white section of the English-Japanese dictionary, which includes explanations such as sugar and sweet, and is associated with the image of young people’s pure love and sugar.
Handkerchiefs are also popular as gifts for White Day.
According to a survey conducted by Comic Seymour in February 2016, the amount of money women in their 20s and 30s want in return for White Day is “less than 500 yen” at 27%, followed by “500 yen to 1,000 yen”. It was 24% of “less than yen”.
According to a February 2016 survey conducted by Ginza Diamond Shiraishi, a bridal jewelry specialty store, the average budget for men between the ages of 20 and 35 to return their favorite person (favorite) on White Day is the most frequent value. was 22.0% for “500 yen to less than 1000 yen”, followed by 21.2% for “1,000 yen to less than 2,000 yen”.
In addition, 33.6% of men answered that they would “repay a little more than what they received,” followed by 28.0% that they would “same amount” and 14.4% that they would not repay.
According to a survey conducted in January 2016 by the Hanshin Department Store Umeda Main Store, 45% of women answered that they were “disappointed” in return for White Day.
In addition, 85% of women answered that they wanted to find out their preferences in advance.
In addition, according to the same survey, the most common budget for men to reciprocate was 33% who said “equivalent to the amount received”, followed by 27% who said “double”, and 25% who said “1.5 times”. .
And it seems that 49% of the men answered that they would “research women’s preferences.”
Unlike Valentine’s Day, which is dominated by chocolate, White Day is not only about confectionery, but in recent years, non-food gifts have become popular.
According to JION’s 2017 survey, confectionery was the second most popular choice among women, followed by accessories such as earrings and necklaces.
A long time ago, N also gave me a wry smile when I received an accessory case that would make elementary school students happy.
I am happy that you chose it for me, so I am still using it, but it is quite difficult.
Some Asian countries also have the custom of White Day.
In Chinese, it is written as “White Lovers’ Festival”.
Gifts in Taiwan are varied, and in Korea, baskets decorated with sweets are the standard return gift.
It seems that this custom is not seen in other countries around the world such as Europe, America, Oceania, South America and Africa.
It’s not universal.
It might be interesting to give antiques as a gift by changing the rules a little.
See you soon
********************
ご実家の整理やお片付けなどをされている方のご相談などが多くございます。
これから春に向かってお片付けを検討されていらっしゃる方も。
風光舎では古美術品や骨董品の他にも絵画や宝石、趣味のお品など様々なジャンルのものを買受しております。
お片付けをされていて、こういうものでもいいのかしらと迷われているものでも、どうぞお気軽にご相談下さいませ。
また風光舎は、出張買取も強化しております。ご近所はもちろん、愛知県内、岐阜県、三重県その他の県へも出張いたします。
まずは、お電話お待ちしております。
愛知県名古屋市千種区姫池通
骨董 買取【古美術 風光舎 名古屋店】
TEL052(734)8444
10:00-17:00 OPEN
#高価買取#無料査定#出張費無料#お片付け#生前整理#遺品整理#古美術#骨董#ご相談ください