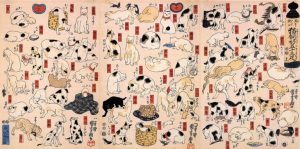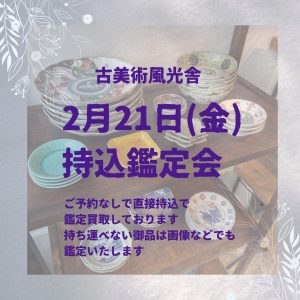ミトコンドリア意識してますか?(愛知県名古屋市千種区姫池通 骨董買取 古美術風光舎)
2025.02.26
ここ数日の暖かい日差しに、街ゆく人々も心なしか軽やかな装いに変わった気がいたします。私はといいますと、コートやセーターに包まれてすっかり油断していた体が重くなっておりまして、どうしたものかと思いながらも、冬は寒さで動きが鈍くなるから仕方がないよねと自分に言い訳をしております。ところがその言い訳は通用せず、実は冬はダイエットに最適な季節なのだそうです。

寒い冬の間は体温を保つために消費エネルギーが増加するそうで、自然と基礎代謝が上がっているのだとか。
基礎代謝とは体が安静にしている時でも消費されているエネルギーで、冬は体温を一定に保とうとして基礎代謝が上昇し脂肪が燃焼しやすく、瘦せやすい状態なのだそうです。
冬に体重が増加すると感じるのは、運動不足もありますが、やはりクリスマスや年末年始の行事などでご馳走を食べすぎる傾向にあるから、だそうです。普段あまり運動をしない人ほど、掃除やウオーキングなどの軽い運動でも基礎代謝を更に上げる効果があるのだとか。
この基礎代謝を考えるにあたり最近特に注目されているのが「ミトコンドリア」なのだそうです。皆さま一度は耳にされたことがある言葉かと思います。私も教科書のあのソラマメのような図を思い浮かべるのですが、確かに最近「飲むミトコンドリア」などの文字も見かけるようになり、ミトコンドリアとは?という疑問が湧いております。
調べれば調べるほど驚きの連続でしたので、よければお付き合いください。
ミトコンドリアは人間の赤血球以外の全ての細胞内に存在するのですが、驚くことに元々は人の祖先とは別の生物で、酸素を使ってエネルギーを生産し、独立して生きていたとか。それが約25億年前に人の祖先の古細菌と共生する道を選び、今も人間の体の中で生き続けています。
そういえば、昔ベストセラーとなった「パラサイト・イブ」という瀬名秀明のホラー小説がありました。映画にもなりましたが、人間の体を乗っ取り、征服しようとするイブと呼ばれる生物がミトコンドリアだとされています。
当時はこんな斬新で恐ろしいストーリをよく考えつくなと思っていましたが、実は生物学に沿った現実的なお話でもあったのですね。
もちろんミトコンドリアは今のところそのような恐ろしい存在ではなく、どちらかというと私たちの生命活動になくてはならない働きをしてくれています。もともと酸素が苦手だった人類の祖先の代わりに酸素を取り込み、エネルギーを作り続けてくれています。そして人の筋肉の細胞内のミトコンドリアは運動すればするほど数が増え、それに伴い基礎代謝が上昇するのだそうです。
マラソン選手には細い体形の人が多く、長距離を走り抜くエネルギーがどこから来ているのだろう不思議でしたが、訓練により細胞内のミトコンドリアがかなり増えている状態なのだそうです。
常に泳ぎ続けるマグロの身が赤いのも、ミトコンドリアに酸素を運ぶタンパク質の色が赤いからだそうで、逆に海底などで身を身をひそめるカレイやヒラメなどは身が白いのだとか。
人が常に呼吸をするのも、ミトコンドリアに酸素を送るためということになりますね。
私たちの体は細胞の核の中にあるDNAによりプログラムされていますが、細胞内のミトコンドリアは核の中のDNAとは別の、単独生活をしていた頃のミトコンドリア独自のDNAを今も持ち続けているといいます。なんだか体の中に違う生物がいるような不思議な感覚になってきました。
しかもそのミトコンドリアのDNAは母親からしか受け継がないそうで、今いる人間の母親のミトコンドリアDNAを辿っていくと、アフリカの一人の女性にたどり着くのだそうです。それが世にいう「ミトコンドリア・イブ」正確には「ミトコンドリア・イブ集団」とも言われています。
人類の母とされる「アフリカのイブ」の有名なお話。私は何度考えても理解ができず、そんな訳ないよねと常々思っていましたが、少し見えてきました。人類の母というよりは、ミトコンドリアDNAの母なのですね。
それにしましてもミトコンドリア、何十億年前によくぞ共生しようと決心してくれました。なんだか途方もないお話にも聞こえますが、実際に自分の体の中に受け継がれているのかと思うと、雑に扱わず、労わってあげなくてはという思いが強くなります。
それでは、また次の機会に。(スタッフH)
With the warm sunshine of the past few days, people on the streets seem to have changed into lighter and lighter clothing. I have been wondering what is wrong with my body, which has been completely careless wrapped in coats and sweaters, but I have been making excuses to myself that it can’t be helped because the cold makes me slow down in the winter. However, that excuse doesn’t work. In fact, winter is the best season for weight loss.
During the cold winter months, energy consumption increases in order to maintain body temperature, which naturally increases basal metabolism.
Basal metabolism is the energy that is consumed even when the body is at rest, and in winter, the body tries to maintain a constant body temperature, which increases basal metabolism, making it easier to burn fat and lose weight.
The reason why people feel that they gain weight in winter is not only because of lack of exercise, but also because they tend to eat too much food at Christmas and New Year’s. The less exercise people usually do, the more they clean their house. For those who do not usually exercise, even light exercise such as cleaning or walking can raise basal metabolism even more.
Mitochondria” have been the focus of much attention in recent years when considering basal metabolism. I am sure everyone has heard of this term at least once. I also think of that solanaceous figure in textbooks, and it is true that recently I have seen the words “drink mitochondria” and other such terms, which begs the question, what is a mitochondria? The more I looked into it, the more I was surprised.
The more I looked into it, the more I was surprised, so please bear with me if you would like to know more.
Mitochondria are present in all cells except human red blood cells, but surprisingly, they were originally a separate organism from our human ancestors and lived independently, using oxygen to produce energy. Then, about 2.5 billion years ago, they chose to live in symbiosis with the archaea of our human ancestors, and they continue to live inside our bodies today.
Come to think of it, there was a horror novel by Hideaki Sena called “Parasite Eve,” which became a bestseller a long time ago. It was made into a movie, and it is said that mitochondria are the creatures called Eve that try to take over and conquer the human body.
At the time, I wondered how they could come up with such a novel and frightening story, but in fact, it was also a realistic story in line with biology.
Of course, mitochondria are not such a terrifying existence at the moment, but rather they play an indispensable role in our biological activities. They take in oxygen and continue to produce energy on behalf of our human ancestors, who were originally oxygen-phobic. And the more we exercise, the more mitochondria in our muscle cells increase in number, which in turn increases our basal metabolism.
Many marathoners have thin physiques, and I have wondered where they get the energy to run long distances, but it seems that the mitochondria in their cells have increased considerably through training.
The reason why the flesh of tuna, which swims constantly, is red is because the protein that carries oxygen to the mitochondria is red in color, while flounder and flatfish, which hide themselves on the ocean floor, have white flesh.
The reason we breathe constantly is to send oxygen to the mitochondria.
Our bodies are programmed by the DNA in the nucleus of the cell, but the mitochondria in the cell still carry their own DNA from when they lived alone, separate from the DNA in the nucleus. It is somewhat mysterious, as if there is a different organism inside the body.
Moreover, it is said that mitochondrial DNA can only be inherited from the mother, and if you trace the mitochondrial DNA of the mother of a human being today, you will reach a woman in Africa. This is what is known as “mitochondrial Eve,” or more accurately, the “mitochondrial Eve population.
The famous story of “African Eve,” the mother of humanity. I could not understand it no matter how many times I thought about it and always thought that it could not be true, but now I see a little more. Rather than the mother of humankind, she is the mother of mitochondrial DNA.
And yet, I am amazed that mitochondria decided to coexist with us billions of years ago. It sounds like an extraordinary story, but when I think about the fact that it is actually passed down in my body, I feel strongly that I should take care of it and not treat it roughly.
See you next time. (Staff H)
*****************
ご実家の整理やお片付けなどをされている方のご相談などが多くございます。
お片付けなどくれぐれもご無理のないようになさってくださいませ。
風光舎では古美術品や骨董品の他にも絵画や宝石、趣味のお品など様々なジャンルのものを買受しております。
お片付けをされていて、こういうものでもいいのかしらと迷われているものでも、どうぞお気軽にご相談下さいませ。
また風光舎は、出張買取も強化しております。ご近所はもちろん、愛知県内、岐阜県、三重県その他の県へも出張いたします。
まずは、お電話お待ちしております。
愛知県名古屋市千種区姫池通
骨董 買取【古美術 風光舎 名古屋店】
TEL052(734)8444
10:00-18:00 OPEN
#出張買取#骨董#古美術#骨董品#絵画#版画#茶道具#刀剣#彫刻