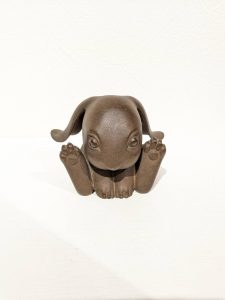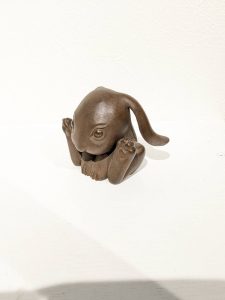明日十五夜お月さまは見えるでしょうか(愛知県名古屋市千種区姫池通 骨董買取 古美術風光舎)
2025.10.05

月の美しい季節になりました。
明日は中秋の名月です。中秋の名月とは、旧暦の8月15日に見える月のことで、十五夜とも呼ばれ、2025年は10月6日が中秋の名月にあたります。旧暦の秋にあたる7月、8月、9月の真ん中の月である8月はちょうど秋の真ん中にあたるため、「中秋」と呼ばれます。
ちなみに似た言葉に「仲秋」というものがありますが、こちらは旧暦の8月全体をさす言葉。そのため、8月15日の月のことを「中秋の名月」とは言いますが、「仲秋の名月」とは言いません。
「中秋の名月」「お月見」と言うと、満月を見るイベントのイメージですが、実は必ずしも満月になるわけではありません。2025年の中秋の名月は10月6日(月)ですが、実際に満月となるのは翌日の10月7日(火)です。
これは、月が地球の周りを回る軌道が円軌道ではなく、わずかに楕円軌道だから。そのため、新月から満月までの日数は13.9~15.6日と1日以上の幅があります。一方で、旧暦では月の満ち欠けの周期の約半分にあたる15日が満月であると考えられていて、天文学的な意味での満月がいつになるかは載っていませんでした。そのため、名月の日と満月の日が異なる年がときどきやってくることになります。
ちなみに、次に中秋の名月と満月が同じ日付になるのは2030年だそうです。
十五夜秋のお月見は別名「芋名月(いもめいげつ)」とも呼ばれ、ちょうど秋の収穫を祝うタイミングの暦としても親しまれてきました。ちょうど新芋(里芋)の収穫の時期に訪れる十五夜に、実りを祝うお供え物として里芋が供えられていました。そこから地域によっては芋名月とも呼ばれるようになったそうです。お月見のお供え物として有名なのはお月見団子ですが、団子も同じように収穫の祝いを表しています。
お月見の文化は中国から伝わったと言われています。平安時代に貴族の間に伝わり、たちまち大ブームに。やがて江戸時代になるとお月見文化は庶民にも浸透し、今では私たちの馴染みのある文化のひとつとなっています。
そして2025年の10月6日は、暦の上で年に数回しかない最強の吉日である「天赦日」と「一粒万倍日」が重なり、そのパワーも倍増する日となっていますよ。
満月は年に12~13回ありますが、古来より、月は「豊かさ」や「金運」を司る存在とされており、特に十五夜の満ちた月は、そのエネルギーが最も強くなるといわれています。秋の月ばかりが名月ともてはやされるのは、ただ単に空気が澄んで、月が綺麗に見えるからだけではないのかもしれませんね。
また、6日(月)夜は、中秋の名月の近くに「土星」の姿も見ることができるのだそう。月がとても明るいため、0.6等の土星は少し見づらいかもしれないとのことですが、お月見の際には土星も一緒に探してみてくださいね。
来たる最強開運日。ドキドキしながら宝くじを購入してみるのも良し。行ってみたかった神社に参拝に行ったりして、願い事をしてみるのも良し。もちろん、十五夜のお月さまも見上げてみてくださいね。
ではでは、また。(スタッフT)
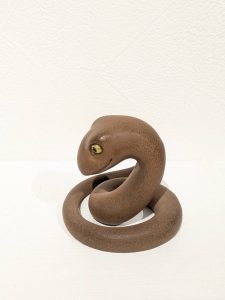
The season of beautiful moonlight has arrived.
Tomorrow is the Mid-Autumn Moon. The Mid-Autumn Moon refers to the moon visible on the 15th day of the eighth month of the lunar calendar, also called the Fifteenth Night. In 2025, the Mid-Autumn Moon falls on October 6th. August, being the middle month of the lunar autumn months (July, August, and September), coincides with the very center of autumn, hence the name “Mid-Autumn.”
Incidentally, there is a similar term, “Nakashū” (仲秋), which refers to the entire eighth month of the lunar calendar. Therefore, while we say the moon on the 15th is the “Mid-Autumn Full Moon,” we do not say it is the “Nakashū Full Moon.”
While “Mid-Autumn Full Moon” and “moon viewing” (お月見) evoke images of events to see the full moon, it does not necessarily mean the moon will be full. The 2025 Mid-Autumn Moon falls on Monday, October 6th, but the actual full moon occurs the following day, Tuesday, October 7th.
This is because the moon’s orbit around Earth is not circular but slightly elliptical. Consequently, the number of days from new moon to full moon varies between 13.9 and 15.6 days, a difference of over one day. Meanwhile, the lunar calendar traditionally considers the 15th day—roughly half the lunar cycle—as the full moon, without specifying the astronomical date. Consequently, years occasionally occur where the festival date and the actual full moon differ.
Incidentally, the next time the Mid-Autumn Festival and the full moon fall on the same date is said to be 2030.
The Fifteenth Night Autumn Moon Viewing is also known as the “Potato Moon” (Imo Meigetsu). It has long been cherished as a calendar event coinciding with the celebration of the autumn harvest. During the Fifteenth Night, which falls right around the harvest season for new potatoes (taro), taro was offered as an offering to celebrate the bounty. This is why it came to be called the Potato Moon in some regions. While moon-viewing dumplings are the most famous offering for moon viewing, these dumplings also symbolize the celebration of the harvest.
The culture of moon viewing is said to have originated in China. It spread among the aristocracy during the Heian period and quickly became a huge craze. By the Edo period, moon viewing culture had permeated the common people, and it is now one of our familiar cultural traditions.
Furthermore, October 6, 2025, coincides with two of the most auspicious days in the calendar—Tensha-bi (Day of Heavenly Pardon) and Ichiryūmanbai-bi (Day of Tenfold Increase)—which occur only a few times a year. This makes it a day of doubly potent energy.
While there are 12 to 13 full moons each year, the moon has long been regarded as a symbol of abundance and financial fortune. The full moon on the fifteenth night is said to possess the strongest of this energy. Perhaps autumn moons aren’t just celebrated as “famous moons” simply because the air is clear and the moon looks beautiful.
Also, on the evening of the 6th (Monday), Saturn will be visible near the Mid-Autumn Full Moon. Since the moon will be very bright, Saturn (magnitude 0.6) might be a bit hard to spot, but try looking for it while you’re enjoying the moon viewing.
The upcoming day of peak fortune. Why not buy a lottery ticket with bated breath? Or visit that shrine you’ve been meaning to go to and make a wish? And of course, don’t forget to look up at the full moon on the fifteenth night.
Well then, see you later. (Staff T)
*******************
ご実家の整理やお片付けなどをされている方のご相談などが多くございます。
お片付けなどくれぐれもご無理のないようになさってくださいませ。
風光舎では古美術品や骨董品の他にも絵画や宝石、趣味のお品など様々なジャンルのものを買受しております。
お片付けをされていて、こういうものでもいいのかしらと迷われているものでも、どうぞお気軽にご相談下さいませ。
また風光舎は、出張買取も強化しております。ご近所はもちろん、愛知県内、岐阜県、三重県その他の県へも出張いたします。
まずは、お電話お待ちしております。
愛知県名古屋市千種区姫池通
骨董 買取【古美術 風光舎 名古屋店】
TEL052(734)8444
10:00-17:00 OPEN
#出張買取#骨董#古美術#骨董品#絵画#版画#茶道具#刀剣#彫刻