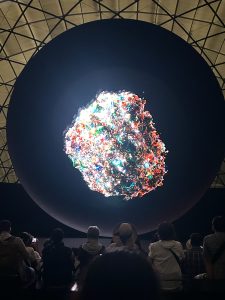8月が終わっていく、でも暑い。(愛知県名古屋市千種区姫池通 骨董買取 古美術風光舎)
2025.08.31
本日は8月31日。

次に言いたいことはわかっています。
この暑さはなに?ですよね。
口にしても暑さは続くのでできれば口にしたくなかったのですが、9月に入ろうとしているにもかかわらずこの猛暑ですと、ちょっと挫けそうになってきました。
汗を拭きながらではありますが、本日は少し涼しくなるようなつぶやきをしていきましょうか。
最近夜に窓をあけると、何という虫か分かりませんが微かに虫の鳴き声がしてきます。虫の音が聞こえるなんてどこに住んでいるんだ?と思われそうですが笑。まだまだ暑い日が続くにもかかわらず、虫の音がどこからともなく響いてきますと、暑さでざわついていたメンタルが、どとこなくスーっと静まって、一瞬暑さを忘れさせてくれます。「虫の音=秋だよ、涼しくなるよ」と、大体の人はインプットされていると思いますが、このところの暑さですと「もうすぐ涼しくなるんだよね?」と、やや逸る気持ちで虫に確認したいような気分にもなります。
聞くところによると、虫の鳴くテンポの変化から現在の気温を知ることができるようでして。
虫は変温動物なので、気温が下がると羽を動かすテンポが遅くなり鳴き声もゆっくりになってくるようです。このテンポの遅さが秋の涼しさを感じさせる一因となるのですが、案の定このところの虫の音はせわしなく鳴いている気がします。
また、秋の虫は、おおよそ15℃から30℃くらいの気温で鳴き、15℃を下回ると鳴かなくなる傾向があるようですから、夜の気温は流石に30℃下回っていることなのか?いや暑いけど。
以前にもつぶやいたと思うのですが、日本人は虫の声を言語のように左脳でとらえるようです。(他国の人には雑音に聞こえるようですね)そこから想像を広げ、風流として感じ取ると考えられているようなのですが、自分ももれなく虫の音に思いを馳せてはみたくなるはなるですが、「もうすぐ涼しくなるんだよね?」などと風流とは違って暑さのせいでどこか愚痴っぽい気持ちが漏れてしまいました。
ゆっくりとした虫の音を、ゆったりと風流な気持ちで聞くことができるのはいつのことだろう。
それではごきげんよう(スタッフY)

It’s August 31st. I know what you’re thinking: “What’s with this heat?”
I really didn’t want to talk about it because it doesn’t make the heat go away. But even though we’re about to enter September, this sweltering heat is starting to get to me. So, even as I wipe the sweat from my brow, maybe a few cool thoughts will help.
Lately, when I open the window at night, I can hear the faint chirping of insects. You might be wondering where I live to hear that sound, haha. But despite the relentless heat, the sound of the insects somehow soothes my overheated mind, making me forget the temperature, even if just for a moment. Most of us are conditioned to hear “the sound of insects” and think “autumn is here, it’s getting cooler.” But with the recent heat, I feel a little impatient and want to ask the insects, “It’s going to get cooler soon, right?”
I’ve heard that you can tell the current temperature by the tempo of an insect’s chirping. Since insects are cold-blooded, as the temperature drops, the rhythm of their wings slows down, and their chirping becomes more leisurely. This slower tempo is part of what makes us feel the coolness of autumn. But, predictably, the insects’ chirping sounds quite frantic lately. Also, autumn insects tend to chirp between 15°C and 30°C and stop when it gets below 15°C. So maybe the night temperature is finally dipping below 30°C? It sure doesn’t feel like it.
I think I mentioned this before, but Japanese people process the sound of insects in the left side of their brains, like a language. (For people in other countries, it just sounds like noise.) From there, we are thought to expand our imagination and feel a sense of elegance and refined taste. I’m certainly no exception; I find myself contemplating the sounds of the insects. But thanks to the heat, my feelings of refined taste are getting replaced with a more cranky, almost whiny thought: “It’s going to get cooler soon, right?”
I wonder when I’ll be able to listen to the slow, leisurely chirping of insects with a calm, elegant heart again.
Farewell for now(Staff Y)

*******************
ご実家の整理やお片付けなどをされている方のご相談などが多くございます。
お片付けなどくれぐれもご無理のないようになさってくださいませ。
風光舎では古美術品や骨董品の他にも絵画や宝石、趣味のお品など様々なジャンルのものを買受しております。
お片付けをされていて、こういうものでもいいのかしらと迷われているものでも、どうぞお気軽にご相談下さいませ。
また風光舎は、出張買取も強化しております。ご近所はもちろん、愛知県内、岐阜県、三重県その他の県へも出張いたします。
まずは、お電話お待ちしております。
愛知県名古屋市千種区姫池通
骨董 買取【古美術 風光舎 名古屋店】
TEL052(734)8444
10:00-17:00 OPEN
#出張買取#骨董#古美術#骨董品#絵画#版画#茶道具#刀剣#彫刻